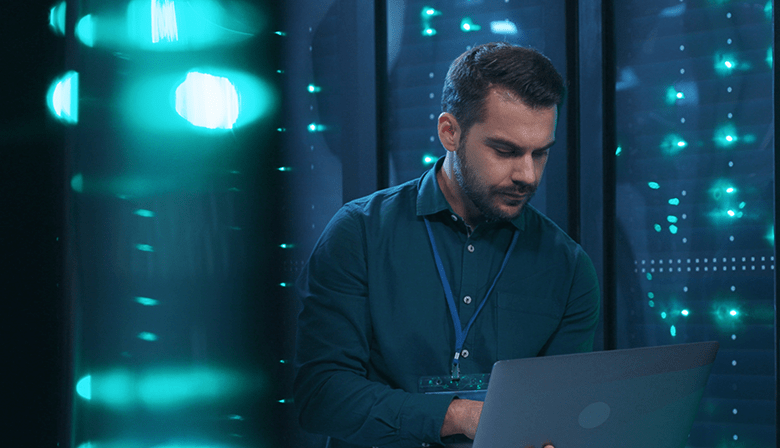目次
ITハイジーンとは?
ITハイジーンは、IT環境のセキュリティ維持や強化のための基準や手法を指します。
ITハイジーンが注目される背景
ITハイジーンが注目される背景には、企業のデジタル化とそれに伴うサイバー攻撃の増加があります。近年、企業のIT環境はますます複雑化し、多くのデバイスやシステムがネットワークにつながることになりました。このような状態が続く中、セキュリティの脆弱性が増大し、悪意のある攻撃者にとって魅力的なターゲットとなる企業が増えています。
このため、企業はITハイジーンの概念を導入し、セキュリティを強化することが求められています。具体的には、IT資産の管理、エンドポイントの保護、シャドーITの管理、従業員へのセキュリティ教育などが含まれます。これらの対策を実施することで、企業はサイバー攻撃のリスクを低減し、インシデントの発生を防ぐことができます。
さらに、ITハイジーンは企業の信頼性やガバナンスの強化にも寄与します。適切なセキュリティ対策を講じることで、企業は顧客やパートナーからの信頼を獲得し、ビジネスの持続可能性を高めることができます。これにより、企業全体の競争力が向上し、デジタルトランスフォーメーションの一環として重要な役割を果たします。
企業におけるITハイジーンの重要性
企業におけるITハイジーンの重要性は、セキュリティリスクの減少と効率化にあります。未管理端末やシャドーITの存在は、企業のセキュリティ管理において重大な脆弱性を生じさせます。これらの要素を適切に管理することは、企業のセキュリティを維持し、サイバー攻撃のリスクを最小限に抑えるために不可欠です。
また、ITハイジーンを導入することで、企業のIT資産のガバナンスが強化されます。IT資産の適切な管理は、組織全体の運営効率を向上させるだけでなく、法規制遵守や内部統制の面でも大きなメリットがあります。これにより、インシデント対応が迅速かつ効果的に行えるようになり、企業の信頼性が増します。
さらに、従業員へのセキュリティ教育も重要な要素です。従業員がセキュリティ意識を高めることで、日常業務におけるセキュリティリスクの発生を防ぎ、企業全体でセキュリティ文化を醸成することができます。継続的なIT資産のモニタリングによって、新たな脅威への対応力も強化され、企業のセキュリティ体制が一層向上します。
ITハイジーンを怠るリスクとその影響
ITハイジーンを怠ることは、企業にさまざまなセキュリティリスクをもたらします。それにより、重要なデータの漏洩やシステムの停止などの重大な影響が発生する可能性があります。
未管理端末のリスク
企業が把握・管理していない未管理端末は、サイバー攻撃の格好の標的となり、組織のセキュリティ体制における重大な脆弱性となります。これらのデバイスは、適切なセキュリティ対策が施されていない場合が多く、攻撃者にとって侵入しやすい入り口を提供してしまうのです。
例えば、従業員が私物のスマートフォンやノートPCを業務に利用するケースを考えてみます。これらの個人端末が企業のネットワークに接続されると、もし端末がマルウェアに感染していた場合、社内システムへの不正アクセスや機密情報漏洩のリスクが一気に高まります。実際に、管理外のデバイスを経由した攻撃により、大規模なデータ侵害に至った事例も後を絶ちません。
このような事態を回避するためには、組織内の全ての端末を正確に把握し、一元的に管理する体制の構築が不可欠です。同時に、セキュリティポリシーを策定し、従業員一人ひとりがそれを遵守するように、定期的な教育を通じて意識を高めることも重要となります。未管理端末がもたらす危険性を正しく認識し、適切な対策を講じることで、企業のセキュリティレベルを向上させることができます。
シャドーITの問題
シャドーITとは、企業のIT部門が関知しないまま、従業員が業務効率化などを目的に独断で利用するIT機器やクラウドサービスを指します。便利な無料ツールや個人契約のオンラインストレージなどがその典型例です。利便性を求めて導入したこれらのツールが、結果として組織全体のセキュリティポリシーを逸脱し、新たな脅威を生み出すことがあります。
シャドーITが引き起こす最大の問題の一つは、セキュリティ脆弱性の増大です。IT部門の管理下にないツールやサービスは、企業のセキュリティ基準を満たしていないリスクが高く、情報漏洩や不正アクセスの温床となり得ます。例えば、承認されていないファイル共有サービスを利用することで、意図せず機密情報が外部に公開されてしまう危険性があります。また、シャドーITの存在は、組織全体のIT資産管理を著しく困難にします。どの部署で、どのようなツールが、どのように利用されているかを把握できなければ、包括的かつ効果的なセキュリティ対策を施すことは不可能です。
これらの問題を未然に防ぐためには、従業員に対する啓発活動を継続し、ITツールの利用に関する明確な申請・承認プロセスを確立することが求められます。シャドーITの実態を把握し、組織としての統制下に置くことで、潜在的なセキュリティリスクを大幅に低減できます。
ITハイジーンが企業にもたらすメリット
ITハイジーンを実践することにより、企業はセキュリティリスクの削減やガバナンス強化、インシデント対応の効率化など、多くのメリットを享受できます。
IT資産管理によるガバナンス強化
IT資産管理によるガバナンス強化は、企業のセキュリティ向上のための重要な手段です。まず、IT資産管理とは、企業が所有するハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク資源などを適切に管理することを指します。この管理プロセスにより、企業はどの資産が現在使用されているか、どの資産に改修や監視が必要かを正確に把握できます。
IT資産管理の第一歩は、全ての資産をリスト化し、定期的に更新することです。このリストは、資産の寿命、メンテナンス履歴、使用状況などを含み、常に最新の情報を提供する必要があります。これにより、資産の適切な使用と保護が可能になります。
次に、IT資産管理は、不正アクセスやデータ漏洩を防ぐためにも役立ちます。セキュリティポリシーを制定し、全ての資産に対して適切なアクセス権限を設定することで、未管理端末やシャドーITのリスクを軽減できます。これにより、企業のセキュリティ体制が強化され、外部からの脅威に対しても高い防御能力を持つことができます。
さらに、IT資産管理は、インシデント発生時の迅速な対応を可能にします。資産の状態が把握されていれば、問題の発生箇所を特定し、速やかな修復や対応ができるため、業務の中断を最小限に抑えることができます。こうした対策により、企業の業務継続性が向上し、信頼性の確保にも寄与します。
総じて、IT資産管理によるガバナンス強化は、企業のセキュリティ体制を向上させるために欠かせないアプローチです。適切な資産管理を行うことで、企業は内部および外部からの様々な脅威に対して強固な防御策を講じることができ、経営の安定性と信頼性を高めることができます。
セキュリティ運用効率化による工数削減
セキュリティ運用効率化による工数削減は、企業のITハイジーンにおいて非常に重要なポイントです。まず、セキュリティ運用効率化とは、セキュリティ関連のタスクを効率的に管理し、リソースの無駄をなくすことを意味します。これにより、従業員の労働時間の節約や、セキュリティ対策の迅速な実施が可能となります。
具体的には、セキュリティの運用効率化には、ツールやソフトウェアの導入が不可欠です。例えば、セキュリティ情報イベント管理(SIEM)システムを導入することで、企業のITインフラ全体のセキュリティ状況を一元管理できるようになります。このシステムは、リアルタイムで脅威を検出し、迅速に対応するためのアラートを発出するため、セキュリティ担当者の負担を軽減し、効率的な運用が実現します。
また、自動化技術の活用もセキュリティ運用効率化に有効です。例えば、脆弱性のスキャンを定期的に自動実行することで、従業員が手動で行う必要がなくなり、時間と労力が削減されます。さらに、インシデント対応手順を標準化し、自動化することで、問題発生時の対応速度が向上し、被害の拡大を防ぐことができます。
セキュリティ運用効率化のもう一つの方法は、クラウドセキュリティの利用です。クラウドサービスは、高度なセキュリティ機能を提供しており、企業は複雑なセキュリティ設定や管理をクラウドプロバイダーに任せることができます。これにより、専門知識が不足している中小企業でも、効果的なセキュリティ対策を実施することが可能になります。
最後に、セキュリティ運用効率化は人材育成とも関連しています。従業員に定期的なセキュリティトレーニングを提供することで、セキュリティ意識を高め、日常業務におけるセキュリティ対策の実践力を向上させることができます。これにより、従業員が自主的にセキュリティ対策を実施し、結果的に工数削減と効率化が実現します。
以上のように、セキュリティ運用効率化による工数削減は、企業のITハイジーンを強化し、経営資源の有効活用に繋がります。これにより、企業はセキュリティ対策を最適化し、コスト削減と業務効率の向上を達成することができます。
ITハイジーンに取り組むために必要なステップ
まず、自社のセキュリティポリシーを定義し、全社的に共有することが重要です。その後、未管理端末やシャドーITの排除、継続的なモニタリングを実施します。
エンドポイント管理の徹底
エンドポイント管理の徹底は、ITハイジーンの基本となる重要なステップです。エンドポイントとは、社員が使用するPCやスマートフォン、タブレットなどの端末を指します。これらのデバイスは、企業ネットワークの入り口であり、多くの場合、セキュリティの弱点となり得ます。徹底的なエンドポイント管理には、以下のステップが含まれます。
まず、全社員の端末のリストを作成し、未管理端末が存在しないか確認します。未管理端末は、どの端末が企業のネットワークに接続されているかを把握できないため、セキュリティリスクを高めます。次に、セキュリティポリシーを各端末に適用し、従業員が企業の基準に従って端末を使用するようにします。これには、パッチ管理やソフトウェアの更新、アンチウイルスソフトのインストールが含まれます。
さらに、リモートワークが増加する今日では、多要素認証(MFA)の使用がますます重要になります。多要素認証は、不正アクセスを防ぐための追加のセキュリティ対策となります。
社内のセキュリティ教育
社内のセキュリティ教育は、ITハイジーンの成功に不可欠な要素です。従業員一人ひとりがセキュリティに対する意識を持ち、適切な行動を取るための教育を提供することが重要です。セキュリティ教育を効果的に行うためには、以下のポイントを押さえる必要があります。
まず、セキュリティ教育の内容を定期的に見直し、最新の脅威や攻撃手法に対する知識を更新します。これにより、従業員が常に最新の情報を持っている状態を維持できます。次に、教育内容には、基本的なセキュリティ知識から実践的な対策までを含むようにします。例えば、フィッシングメールの見分け方や安全なパスワードの作成方法、データ保護の重要性などです。
また、実践的なトレーニングや模擬演習を行うことで、従業員が具体的なセキュリティ対策を経験する機会を提供します。これにより、理論だけでなく、実際の対応スキルも向上します。さらに、セキュリティ教育の効果を測定し、改善を続けることも重要です。定期的なアンケートや評価を用いて、教育プログラムの有効性を確認し、必要に応じて改善策を講じます。
最後に、セキュリティ教育を全社員に対して定期的に実施し、企業のセキュリティ文化を醸成することが求められます。
継続的なIT資産のモニタリング
継続的なIT資産のモニタリングは、ITハイジーンにおける重要な要素です。企業が保有するIT資産では、ソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク機器などが含まれます。これらの資産を適切に監視することで、セキュリティリスクを低減し、迅速な対応が可能になります。具体的な方法として、以下のポイントがあります。
まず、IT資産のリストを作成し、それぞれの資産の状態を常に最新に保つことが重要です。これにより、どの資産がどのような状態にあるかを把握しやすくなります。次に、ネットワークのトラフィックを監視し、異常な活動を早期に検出するために適切なツールを導入します。これには、侵入検知システム(IDS)や侵入防止システム(IPS)が含まれます。
さらに、ログ管理も重要です。各資産のログを収集し、定期的に分析することで、異常な動きや攻撃の兆候をいち早く発見することができます。自動化されたログ解析ツールを使用することで、効率的な監視が可能になります。また、資産管理システム(ITAM)を導入し、資産のライフサイクルを管理します。これには、資産の購入から廃棄までの全過程が含まれます。
最後に、定期的な監査を実施し、IT資産のセキュリティ状況を評価し、改善が必要な箇所を特定・修正します。これにより、セキュリティ対策を継続的に見直して強化することができます。
ITハイジーンで企業のセキュリティを強化
ITハイジーンの概念を理解し、その実践方法を学ぶことは、企業のセキュリティ体制を強化するために不可欠です。IT環境やシステム管理の衛生を向上させることで、サイバー攻撃のリスクを減少させることができます。特に、未管理端末やシャドーITの問題は企業にとって重大なリスクをもたらします。これらのリスクから企業を守るために、IT資産の管理やエンドポイント管理の徹底、また従業員へのセキュリティ教育が重要です。さらに、継続的なIT資産のモニタリングを行うことで、未知の脅威にも対応する力を持つことができます。
丸紅I-DIGIOグループでは、ITハイジーンの実践を支援するために以下のようなサービスやソリューションを提供しています。
脆弱性診断サービス
脆弱性診断サービスは、システムの脆弱性や設定不備を客観的に評価し、潜在的なリスクを可視化します。ITハイジーンの観点からは、以下のような点で強化に繋がります。
現状把握と可視化: 企業が自身のIT環境における「汚れ」や「不衛生な状態」を正確に把握することを可能にします。これにより、どこから改善を始めるべきか、どの領域にリスクが潜んでいるのかが明確になります。
脆弱性の早期発見と対処: 未修正の脆弱性や不適切な設定は、ITハイジーンを悪化させる最大の要因の一つです。診断によりこれらを早期に発見し、修正することで、攻撃対象領域を減らし、セキュリティレベルを向上させます。
継続的な改善サイクルの確立: 定期的な診断は、一度きりの対策で終わらせず、継続的にITハイジーンを維持・向上させるためのPDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を確立する上で不可欠です。新しい脆弱性が日々発見される中で、常に最新の状態に保つためには継続的なチェックが重要です。
インフラ・グランドデザインサービス
インフラ・グランドデザインサービスは、企業のITインフラ全体の最適化と将来を見据えた設計を支援します。ITハイジーンの観点からは、特に事前予防的な強化に繋がります。
セキュアな設計思想の組み込み: 新規導入や刷新時に、セキュリティを後付けで考えるのではなく、設計段階からセキュリティを考慮したグランドデザインを行うことで、より堅牢で衛生的なITインフラを構築できます。これにより、将来的な脆弱性発生リスクを低減し、運用負荷を軽減します。
標準化と自動化の推進: インフラの標準化は、設定ミスや運用上のばらつきを減らし、管理を容易にします。自動化は、手作業によるヒューマンエラーを削減し、一貫性のあるセキュリティポリシー適用を可能にします。これらはITハイジーンを高いレベルで維持するために不可欠です。
最新技術の活用と陳腐化防止: 古いシステムや技術は、セキュリティパッチの提供が終了したり、新たな脆弱性に対応できなかったりするリスクを抱え、ITハイジーンを悪化させます。グランドデザインを通じて、最新のセキュリティ要件や技術トレンドを取り入れることで、陳腐化を防ぎ、常に健全なIT環境を維持することが可能になります。
運用効率と回復力の向上: 整理され、効率的に運用できるインフラは、インシデント発生時の対応も迅速に行え、事業継続性を高めます。これは、単に「清潔」であるだけでなく、「迅速に回復できる」というITハイジーンの重要な側面を強化します。
自律型AIセキュリティプラットフォーム SentinelOne
SentinelOneは、EDR製品として、脅威を検知するだけでなく、EDR未導入の端末を検知することができます。
知らない間に会社が認識していない端末が持ち込まれるといったことが多くあります。SentinelOneにより、未管理端末をSentinelOneダッシュボード上で検知するだけでなく、隔離も可能です。
また、端末の脆弱性も可視化することができます。エンドポイントセキュリティ、端末管理、脆弱性管理の仕組みが、同じダッシュボード上で管理することができます。
これらのサービスやソリューションを組み合わせることで、企業は現状の課題を洗い出し、将来的にリスクに強い堅牢な基盤を構築するという両面から、包括的なITハイジーン向上を実現できます。結果として、サイバー攻撃のリスクを低減し、安定した事業運営に貢献します。

SentinelOne | セキュリティ事業 | 丸紅I-DIGIO
SentinelOne: 次世代のAI駆動型エンドポイントセキュリティ。高度な脅威を自動検知・対応し、ランサムウェアやゼ…