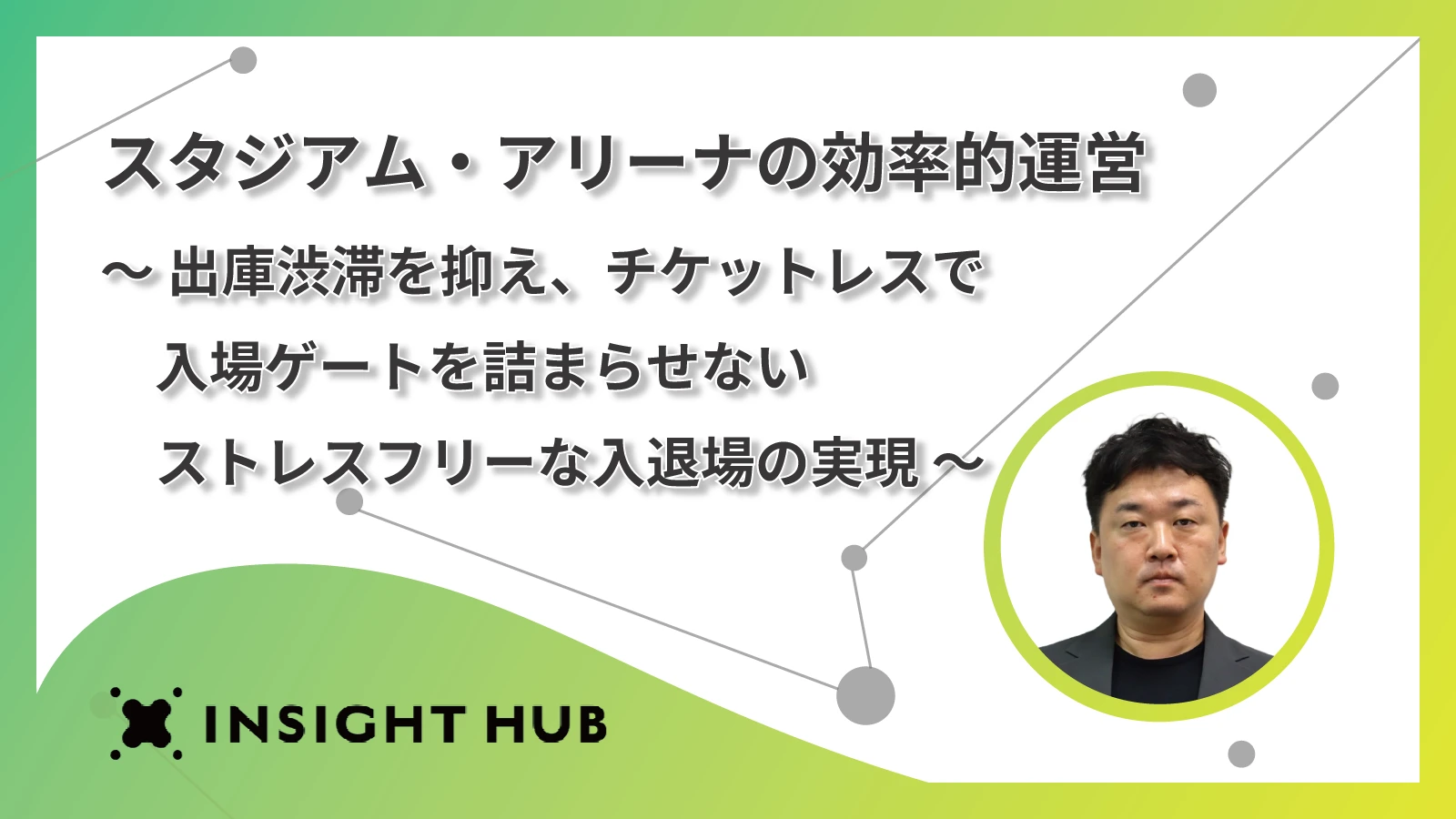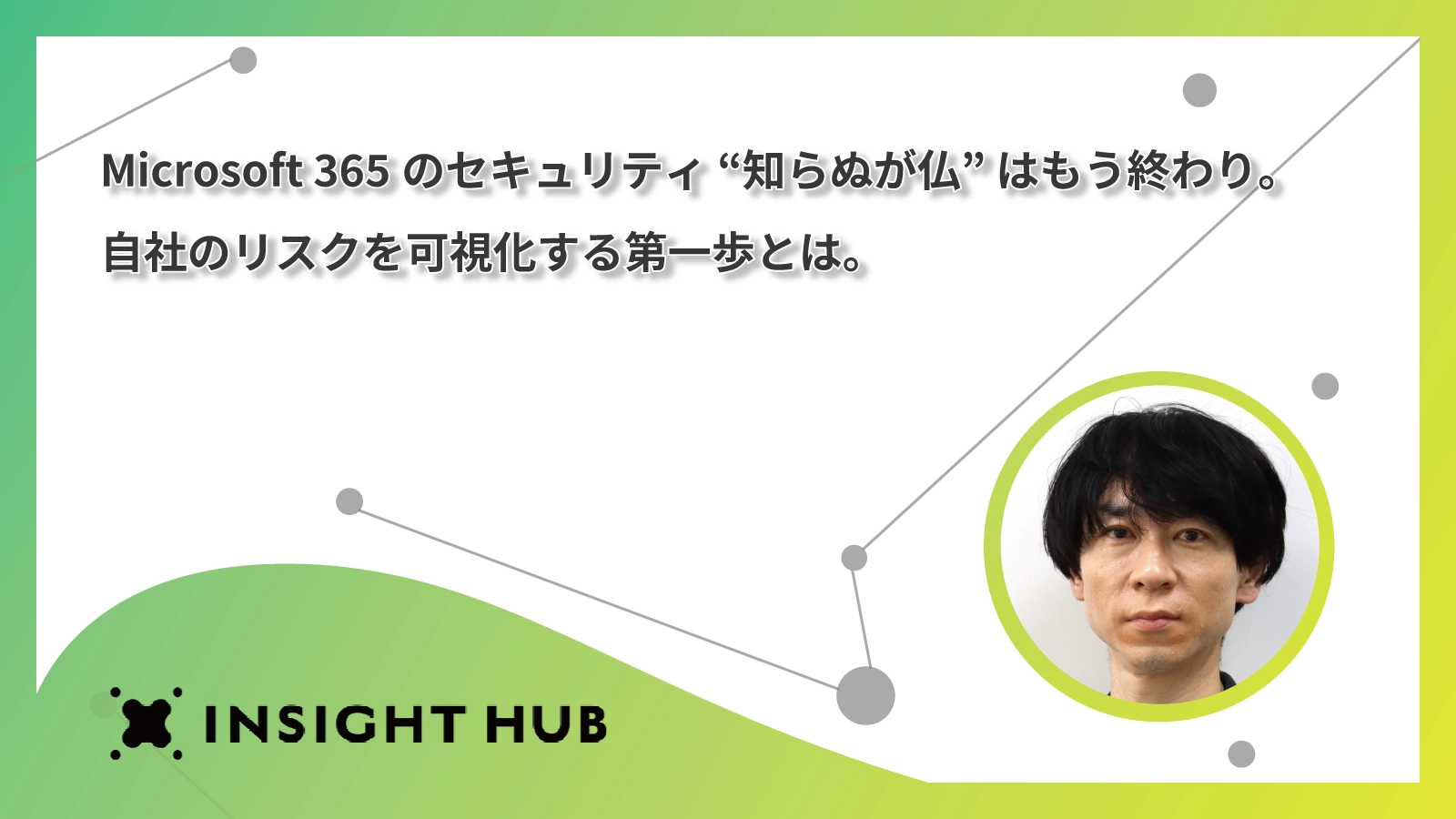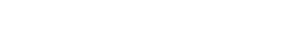今日、日本の社会インフラは老朽化という大きな課題に直面している。平成バブル期に集中的に整備された建物や施設などは築30年以上が経過している。さらに遡って高度経済成長期に整備されたインフラなどであれば、経過期間はさらに長くなり老朽化はより深刻である。2025年、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故の原因は下水道管の腐食と特定され、まさに老朽化問題の露呈する事故であったといえよう。このような老朽化問題は社会インフラだけでなく、同時期に建てられたオフィスビルや商業ビルなども例外ではない。
特にビルの老朽化で問題になっているのが、漏水である。配管などをすべて新しくするとなれば大規模工事が必要となり、またコストも大きなものになる。かといって放置しておけば、ちょっとした水漏れでも、商品や什器への直接的な被害、電気系統のショートによる火災リスク、カビの発生による健康被害、そして何よりもテナントや顧客からの信頼失墜という大きな損害につながりかねない。多少なりとも漏水問題に懸念があるのなら、先延ばしにすることなく、できるだけ早く対策することが求められる。
そこで本稿では、施設管理のDXを推進するIoTプラットフォーム「MAIDOA plus」と先進的な漏水センサーを組み合わせることで実現する、低コストかつ迅速な漏水問題対応について、丸紅I-DIGIOグループ IT基盤サービスセグメント エッジソリューション事業室 ビジネスIT推進課 課長 澤田 勝美に話を聞いた。
漏水対策が課題となる背景には、「建物の老朽化」「商業施設におけるテナント入れ替え」「人手不足」がある
――まず、漏水を検知する仕組みなどが求められる背景について、教えてください。
澤田 漏水に関する仕組みが求められる背景については、大きく三つあると考えています。
一つは、建物の老朽化です。オフィスビルの需要が高まった平成バブルの頃に建てられたビルなどが、築30年以上になり、さらには高度経済成長期にも多くのビルなどが建てられ、それらも老朽化は深刻です。当然、建物だけでなく設備の老朽化問題も顕在化してきており、ほとんどのビルがもつ空調機器や給排水配管といったところでの漏水が大きな問題になることが多いのです。
そして二つめとしては、商業施設などにおけるテナントの入れ替わり時に、これまでアパレルなどだった区画が、飲食店など水道利用が必須のテナントに替わるような際は、新たな漏水リスクを発生させることになるので、しっかりとした漏水対策が欠かせないという背景があります。
そして三つめは、少子高齢化による人手不足という背景です。これは老朽化を背景とした漏水対応とも関係してくるのですが、建物の老朽化に伴う漏水対策としては、空調周り、配管周りの保守点検業務が重要になります。そして、この保守点検業務は、従来は人的な点検作業に頼っていました。老朽化する建物が増えれば、点検人員の必要数も増えますが、この分野でも人手不足が深刻化している状況です。さらに人員を確保できたとしても人件費が高騰しており、コスト負担も増大してしまいます。
こうした「建物の老朽化」「テナント入れ替え時の漏水リスクの増加」「人手不足による保守体制の悪化および人件費増大」という三つの背景により、従来の漏水対策では立ち行かない状況になっているのです。
自己発電型の無線センサーが最適解となる
――そのような三重苦とでもいうべき状況において、より低コストで効率的に漏水対策を施すにはどうすればよいのでしょうか。
澤田 このような背景の元では、簡単に後付けできて、保守点検も省力化あるいは無人化でき、かつ低コストで導入できる漏水検知センサーを設置して、わずかな水漏れもどこで発生しているのかを早期に検知し、迅速な対処ができるようにすることが重要です。
特に、簡単に後付けができることはとても重要です。実際問題としては、大々的に、つまり建物全体で配管工事をするようなことは、コスト面でも、営業面(工事中、テナントが営業できなくなってしまう)でも、とても大変です。後付けで、工事も簡単に行えることは大きなメリットになります。

――簡単に後付けできて、コストもリーズナブルで、それでいて信頼性の高い漏水検知システムとしてはどのようなものがよいのでしょうか。
澤田 漏水検知センサーには、大掛かりな工事が必要な「有線型」と、後付けに適した「センサー設置型」があります。さらに一般的なセンサー設置型システムは、センサー自体に電力を供給するための電源工事が必要になります。これでは、センサーの設置自体は簡単でも、結局は配線工事の手間とコストが発生してしまい、本当の意味で「簡単」とはいえません。
そこで私たちが最適解としてたどり着いたのが、電源工事も不要で、かつ電池交換も一切不要な自己発電型の無線センサーです。これは、センサー自体が動作に必要な微弱な電力を自ら作り出す「エネルギーハーベスティング」という技術を応用したもので、まさに「設置するだけ」で設置が完了します。これにより、導入時の初期費用(イニシャルコスト)を劇的に削減できるだけでなく、運用開始後のメンテナンスも不要になるため、電気代や電池交換の人件費といったランニングコストの圧縮にも大きく貢献します。停電時にも問題なく機能するというのも、災害時のリスク管理を考えると非常に大きなメリットです。
私たちが採用しているセンサーは、その中でも特にユニークなリボン型というもので、文字通りリボン。イメージとしては靴紐のような柔軟な形状のものです。これを漏水リスクのある配管の接続部分や、バルブの継ぎ目といった箇所に巻き付けるだけで設置することが可能です。
このセンサーの検知メカニズムも非常にユニークです。わずか3滴程度の水がこのリボンに触れると、センサー内部の特殊な物質が水と化学反応を起こして微弱な電力を発生させ、その信号を無線で発報する仕組みになっています。物理的なスイッチなどを使わないため誤報が少なく、漏水の発生を極めて初期の段階で、確実に捉えることが可能です。
電源不要でメンテナンスフリー。そしてどんな場所にも柔軟に設置できる「自己発電型無線リボンセンサー」。これこそが、老朽化した既存施設が抱える複雑な課題を解決するための、最も現実的で効率的な選択肢であると確信しています。
IoTプラットフォーム「MAIDOA plus」との連携が漏水検知を効率化する
――自己発電型無線リボンセンサーが極めて有効であることはよくわかりました。しかし、そのセンサーが発する情報を効率的に受け取り、管理・活用するにはどうすればよいのでしょうか。
澤田 どれほど高性能なセンサーを導入しても、それが単独で存在するだけでは宝の持ち腐れです。センサーが施設の異常を早期に捉える鋭敏な「感覚器」だとすれば、その情報を集約、分析し、管理者に的確な判断材料を提供する「頭脳」となるのが、IoTプラットフォームであるMAIDOA plusです。
MAIDOA plusの最大の特徴は、その圧倒的な「接続性」と「拡張性」にあります。世の中には多種多様なセンサーが存在し、メーカーや製品によって通信規格もデータの形式もバラバラです。通常、異なるメーカーの機器を一つのシステムで統合管理することは非常に困難で、いわゆる「ベンダーロックイン」の状態に陥りがちです。しかし、MAIDOA plusは、特定のメーカーに縛られず、多種多様なセンサーからのデータを円滑に集約でき、センサーデータの一元管理を実現します。
たとえば漏水センサーに関しては、施設内のどこかで漏水が発生し、リボンセンサーが水を検知すると、即座に無線信号を発報します。その信号は、施設内に設置された専用のゲートウェイが受信し、クラウド上にあるMAIDOA plusのサーバーへと送信されます。MAIDOA plus側では、受信したデータから、事前に登録されたセンサーID(無線タグ)と、そのIDに紐づけられた設置場所の情報を瞬時に照合し「どの区画の、どの配管のセンサー」が反応したのかを瞬時に特定します。管理者は、PCやスマートフォン、タブレットなどで表示されたアラートを確認し、迅速な対処を実施することが可能になります。
またMAIDOA plusを導入すれば、漏水検知だけでなく、温度・湿度センサー、電力センサー、監視カメラなど、施設内のさまざまなデータを一つのプラットフォーム上で統合的に扱うことができるので、建物全体、施設全体の管理業務をワンストップで実施することが可能になり、ビル管理・施設管理のDXを飛躍的に高めることにつながります。ですから、最初のきっかけは漏水検知センサーの導入であったとしても、その後の拡張性を考えれば、非常に利便性の高いIoTプラットフォームだといえます。
大規模な改修工事より、簡便な「漏水検知センサー+MAIDOA plus」が効果的
――具体的な導入事例があれば、ご紹介ください。
澤田 築40年を迎えた、ある大型商業施設のケースをご紹介します。この施設では、施設全体の配管の老朽化が深刻な問題となっており、根本的な解決のためには配管の全面的な更新が不可欠でした。施設側もそのことは重々承知しており、25年も前から長期的な更新計画を立案し、実行に着手していました。しかし、計画開始から25年経過しても、まだ全体の半分ほどしか更新工事が進んでいませんでした。原因はやはりテナントの入れ替わるタイミングでしか工事ができないという点にありました。そのため配管の更新ができない区画では常に漏水のリスクがありました。
そこで、「根本的な工事が完了するまでの間、どうやって日々の漏水リスクを管理し、万が一の際の被害を最小化するか」という、非常に現実的かつ切実な課題に対し、私たちはMAIDOA plusと連携した漏水検知システムの導入をご提案しました。

敷設箇所は、工事が完了していない老朽化した配管が残るエリアに限定し、その中でも特にリスクが高いと想定される接続部などに、ピンポイントで自己発電型無線リボンセンサーを設置しました。これにより、全面工事の完了を待つことなく、リスクの高い箇所から優先的に24時間365日の自動監視体制を構築できました。
もちろん、センサー設置作業自体も簡便なので、テナントの営業に一切影響を与えることなく実施できました。施設の休業日を待つ必要も、テナントに特別な協力を仰ぐ必要もなく、円滑に漏水検知体制の構築ができました。
このように、漏水検知センサーとMAIDOA plusを導入したことにより、万が一漏水が発生しても、顧客やテナントからクレームが入る前に、ごく初期の段階で異常を検知できるようになりました。管理者は自身のスマートフォンなどに届くアラートで正確な発生箇所を特定し、直ちにスタッフを現場に派遣することができます。こうした迅速な対処により、浸水などの二次被害を未然に防ぎ、施設の信頼性を維持することにもつながりました。
――漏水は万が一のことであるとはいえ、その万が一が発生してしまうと、ビル等であれば漏電による火災のリスクにもなり、商業施設などの場合には商品への損害など大きな問題につながってしまう。そうしたリスクを、できるだけ低コストで、できるだけ簡便に減らせるのが漏水検知センサーとMAIDOA plusの導入だ。漏水のリスクを感じているなら、一日も早い対策が求められる。
お役立ち資料
本記事に関する資料をダウンロードいただけます。