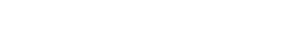防災DXとは?
防災DXとは、防災分野にデジタルトランスフォーメーションを取り入れ、業務の効率化や高度化を図る取り組みです。近年、自然災害の頻発を受けて、多くの自治体や企業がより効果的な災害対応を目指し、防災DXの導入を進めています。
主な取り組みとしては、災害情報の迅速な共有、被害状況の正確な把握、避難所の効率的な運営などが挙げられます。AIやIoT、各種アプリケーションなどの先端技術を活用することで、より高度な防災DXを実現することが可能になります。
防災DXは単なる技術導入にとどまらず、地域全体の防災意識の向上や、住民のデジタルリテラシーの強化にもつながります。また、人手不足や少子高齢化といった社会課題の解決にも寄与し、自治体の災害対応力の強化が期待されています。これにより、災害発生時の迅速な対応や被害の抑制が可能となります。
防災DXが注目される背景
防災DXが注目される背景には、頻発する自然災害と効率的な防災対策の必要性があります。さらに、少子高齢化や自治体職員の人手不足もその要因です。
日本は災害大国
日本は地震、台風、洪水など多様な災害に頻繁に見舞われる災害大国です。歴史を振り返ると、関東大震災や東日本大震災など、重大な災害が幾度となく発生しています。
地震は日本の災害の中でも特に注意が必要なもので、大規模な地震がいつ起きてもおかしくない状態です。政府や地方自治体は、最新の科学技術を導入して地震予測や対策を進めています。
また、台風も毎年のように日本列島を襲い、甚大な被害をもたらしています。2020年の台風19号では、多くの地域が洪水に見舞われ、避難所の不足や人員不足が課題となりました。
これらの頻発する災害に対応するためには、防災DXの導入が不可欠です。デジタル技術を活用することで、安全な避難場所の確保や迅速な情報伝達が可能となり、被害を最小限に抑えることが期待されています。
自治体職員の人員不足
日本の少子高齢化は、自治体職員の人員不足に直結しています。高齢化が進む一方で、若い世代の人口は減少しており、自治体の防災対応力が低下する懸念があります。
自治体職員の人員不足は災害時の緊急対応に大きな影響を与えます。災害発生時には迅速な対応が求められるにも関わらず、人手不足が原因で対応が遅れることがあります。このような状況では、防災DXを導入することで業務の効率化が必要不可欠です。
たとえば、AIチャットボットを活用することで、被災者からの問い合わせに迅速に対応することができます。また、ドローンを利用して被害状況の確認を行うことにより、現場の職員が効率的に対応できるようになります。
さらに、自治体職員の負担を軽減するために、システムの自動化や利用者向けの防災アプリの導入も進められています。これにより、住民自身が災害情報を入手しやすくなり、職員の負担軽減につながります。
防災DXの課題
防災DXには多くのメリットがありますが、いくつかの課題も存在します。
システム導入に伴うコスト、人材不足やスキルギャップ、維持管理やアップデートの問題、プライバシーの保護などが具体的な課題として挙げられます。
導入コスト
防災DXを導入するにあたり、最初に直面する課題はコストです。
システムの構築や機器の購入には高額な費用がかかり、特に中小自治体や企業にとって負担となります。また、一度導入したシステムは定期的なメンテナンスやアップデートが必要であり、これも追加コストを生みます。さらに、導入のための専門知識を持つ人材を雇用することもコストに含まれるため、予算内での適切な計画が求められます。
しかし、長期的に見ると、防災DXによって災害対応の効率が大幅に向上し、費用対効果が実証される可能性があります。たとえば、災害情報の正確な伝達と避難所管理のコスト削減が考えられます。
人材不足やスキルギャップ
防災DXを効果的に運用するためには、適切なスキルを持つ人材が必要です。しかし、自治体や企業においては、特に地方において人材不足が深刻です。
技術の進展に伴い、防災DX関連の知識やスキルも高度化しており、既存の職員では対応が困難となっています。さらに、新技術を使いこなすためには継続的な教育や研修が必要ですが、これにも時間とコストがかかります。
スキルギャップが原因で防災DXの効果が十分に発揮されないこともあるため、組織全体でのスキルアップや適切な人材の確保が課題です。たとえば、ITエンジニアを自治体に招聘し、システム運用をサポートする方法があります。
システムの維持管理やアップデート
防災DXのシステムは日々進化し続けているため、導入後も維持管理や定期的なアップデートが必要です。
たとえば、運用にあたってシステムに新しい機能を追加するためにソフトウェア更新や、ハードウェアの交換、故障対応が必要となる場合があります。
また、セキュリティ対策も重要です。古いシステムは脆弱性が高くなり、サイバー攻撃のリスクが高まります。定期的なアップデートにより、最新の防災DX技術を維持し、安全な運用を確保することが求められます。さらに、システムの維持管理には専門知識を持つ人材の確保も必要となります。
プライバシーの保護
防災DXにおけるデータ活用は規模が大きく、住民の個人情報を扱うことが多いです。そのため、プライバシーの保護は重要な課題です。個人情報の漏洩や不適切な利用は法的問題を引き起こす可能性があるため、厳しいセキュリティ対策が求められます。
また、防災DXシステムを導入する際には、住民に対して透明性を確保し、データがどのように扱われるかを明示する必要があります。具体的には、データ取り扱い方針の公開や、適切なアクセス権限の設定が重要です。たとえば、災害情報を住民に迅速に伝えるアプリは、ユーザーの位置情報を含む必要がありますが、これらの情報が漏洩しないよう適切な管理が必要です。
防災DX導入のメリット
防災DXの導入は、迅速な災害情報の伝達、正確な被害状況の把握、効率的な避難所管理など、多岐にわたるメリットがあります。
緊急情報の迅速な伝達
防災DXを導入することで、緊急情報の迅速な伝達が可能になります。従来、災害発生時における情報伝達は電話やテレビ、ラジオなどに頼っていましたが、これらの方法では情報にタイムラグが発生することが課題となっていました。防災DXでは、デジタル技術を活用してリアルタイムに正確な情報を提供できます。
たとえば、防災アプリを通じて住民に即時にアラートを送信したり、ソーシャルメディアを利用して広範囲にわたる情報共有が可能です。また、自治体や企業が専用のシステムを導入し、災害時の情報を一元的に管理することで、情報の混乱を避けることができます。
緊急情報の迅速な伝達は、住民の安全を確保するだけでなく、救援活動の効率化にも寄与します。たとえば、AI技術を活用し、災害の発生場所や規模を即座に判断し、対策を講じることができます。このように、防災DXが進展することで、一刻を争う災害時に迅速で正確な情報が提供され、被害の軽減に大きく貢献するのです。
被害状況の正確な把握
防災DXの導入で、被害状況を正確に把握することが可能になります。従来の方法では、人手での調査や報告に頼ることが多く、被害状況の把握には時間がかかり、正確性にも限界がありました。
しかし、デジタル技術を活用することにより、たとえば、ドローンやIoTセンサーなどの最新技術を使って迅速に広範囲の状況をモニタリングすることができます。
ドローンを使用することで、災害現場に直接人を派遣することなく、高所や危険地域の状況を効率的に確認し、迅速な対策が可能になります。また、IoTセンサーを活用して建物の状態や被害の度合いをリアルタイムで解析し、具体的なデータを収集することもできます。
こうしたデータを一元管理することで、被害の広がりや集中する箇所を正確に特定し、適切な救援や復旧活動が行えます。従って、防災DXは、被害状況を正確に把握し、その情報を基に迅速かつ効率的な対策を講じるための重要なツールとなります。
効率的な避難所管理
防災DXを導入することで、避難所管理が効率化されます。従来の避難所管理は紙ベースの記録や人手による運営が中心であり、混乱や情報の錯綜が発生しやすいことが課題でした。しかし、デジタル技術を活用することで、避難所の状況をリアルタイムで把握し、効率的に運営することが可能になります。
たとえば、防災アプリを使用して避難所の位置情報や混雑状況を住民に共有することで、最寄りの避難所に迅速に移動できるようになります。また、避難所管理システムを導入することで、避難者の情報をデジタルで一元管理し、食料や物資の配布状況、医療支援の必要性を迅速に把握することができます。
その結果、適切な資源配分が可能になり、避難所運営の効率化が図れます。さらに、AIチャットボットなどを活用して避難者からの問い合わせに対応することで、現場の職員の負担を軽減し、より多くの避難者に迅速に対応できるようになります。効率的な避難所管理は、防災DXの重要なメリットの一つであり、住民の安全と安心に大きく寄与します。
防災DXの具体例
防災DXには多くの具体的な取り組みがあります。以下にその代表的な例を紹介します。
AIカメラ
AIカメラは、防災DXにおいて重要な役割を果たしています。これらのカメラは異常な動きを検知し、災害が発生する前やその後に迅速に対応することが可能です。
たとえば、AIカメラを設置した避難所は、人の密集度や動線をリアルタイムでモニタリングし、適切な行動指示を提供することができます。
さらに、AIカメラは火災や洪水の危険を早期に察知し、警報を鳴らすことによって迅速な避難行動を促します。検知された情報はすぐに関係機関へ送信され、迅速な対応が可能となるため、被害を最小限に抑えることができます。
このように、AIカメラの導入により、自治体や企業は災害時の対応力を大幅に強化することができます。
IoTセンサー
IoTセンサーは、防災DXの中核を担う技術の一つです。これらのセンサーは、地震や台風、水害などの自然災害をリアルタイムで検知することができます。
たとえば、地震が発生した場合、IoTセンサーは即座に震度や揺れの強さを測定し、速やかに情報を伝達します。
また、IoTセンサーは気象情報や水位の変化を監視し続けることで、洪水や土砂崩れの早期予測を可能にします。これにより、住民は災害が発生する前に避難準備を整えることができ、被害を最小限に抑えることができます。
さらに、IoTセンサーはインフラ設備の監視にも利用されており、たとえば、橋やトンネルの状態を常にチェックすることで、災害時に安全性を確保します。
ある自治体では、IoTセンサーを防災インフラに広く展開し、迅速な対応と信頼性の高い情報提供を実現しました。このようにIoTセンサーは、防災DXの効率化と高度化を支える重要な技術として、ますます注目されています。
AIチャットボット
AIチャットボットは、防災DXにおいて新たなコミュニケーションツールとして活用されています。災害時に住民や職員が必要な情報を迅速に得ることができるため、対応力が向上します。
たとえば、AIチャットボットは緊急時の避難指示や災害情報をリアルタイムで提供し、住民が適切な行動を取れるようサポートします。
さらに、AIチャットボットは災害発生前に予防策や準備方法を案内することで、災害への備えを促します。たとえば、地震対策として家具の固定方法や避難バッグの準備方法を尋ねると、適切なアドバイスを提供します。
自治体や企業がAIチャットボットを導入することで、人手不足や業務負担を軽減できます。このようにAIチャットボットは、防災DXにおける効率化と迅速な情報提供を可能にする重要なツールとなっています。
住民向け防災アプリ
住民向け防災アプリは、防災DXの重要なツールとして活用されています。このアプリは、災害時に必要な情報を迅速かつ正確に住民へ伝達する役割を果たします。
たとえば、地震や台風の発生時には、その被害予測や避難指示をリアルタイムで配信し、住民が適切な行動を取れるようサポートします。
また、防災アプリは避難場所の情報や支援物資の配布状況を提供することで、パニックを防ぎ、効率的な避難を促します。
一部のアプリは、ユーザーの位置情報を利用して、最適な避難ルートを案内する機能を備えています。さらに、災害時には家族や友人と連絡を取るためのチャット機能や安否確認機能も搭載されており、安心感を提供します。
ドローンによる被災状況の確認
ドローンは、防災DXにおいて非常に有効なツールとして活用されています。災害発生後に迅速かつ広範囲な被災状況の確認が可能となり、効率的な救助活動や復旧作業を支援します。
たとえば、洪水や地震が発生した際にドローンを飛ばし、被害の全体像を空から監視することで、救助活動の優先順位を決定する助けとなります。
また、ドローンはアクセス困難な場所でも精密なデータを収集することができ、迅速な対応を可能にします。たとえば、山岳地帯や倒壊した建物周辺では、人的な調査が難しい場合がありますが、ドローンを使えば効果的に状況を把握できます。
ドローンによる被災状況の確認は、既に自治体や企業の防災対策を強化する重要な手段となっています。
企業による防災DX活用例
企業が防災DXを進めることは、災害時のリスクを最小限に抑え、事業の継続性を確保するために不可欠です。デジタル技術を活用することで、これまで難しかった迅速かつ的確な対応が可能になります。
ある企業ではAIを活用したチャットボットを導入し、従業員の安否確認や緊急時の連絡を迅速に行える仕組みを構築しました。これにより、有事の際の状況把握と初動対応が大幅にスピードアップしています。
さらに、別の企業ではドローン技術を用いて、工場や事業所の被害状況をリアルタイムで把握する取り組みを進めています。ドローンで撮影された映像は、被害の全体像を素早く把握し、復旧作業の計画を効率的に立てる上で役立っています。
他にも、多くの企業が防災アプリを導入し、従業員への災害情報を迅速に共有しています。これにより、従業員は刻々と変わる状況下でも適切な行動を素早く判断でき、企業全体の安全性が向上しています。
このように、防災DXは企業の安全対策においても極めて重要な役割を担っており、今後もその導入は加速していくでしょう。
防災DXを推進し、未曽有の災害に備える
防災DXの導入は、日本の防災力を根本から強化するための重要なステップです。
防災DXを導入することで災害情報の迅速な伝達や正確な被害状況の把握、効率的な避難誘導などが可能となり、自治体や企業は、自然災害に対してより効果的な対応ができるようになります。
丸紅I-DIGIOグループでは、以下のようなソリューションを提供し、防災DXを推進しています。
災害時の迅速な状況把握を可能にする「TRASCOPE-AI」
災害が発生した際、現場の状況をいち早く、そして正確に把握することは、その後の避難行動や救援活動の成否を大きく左右します。TRASCOPE-AIは、AI画像解析技術を駆使し、異常発生時に迅速な検知を可能とするソリューションです。
具体的には、河川監視カメラの映像から水位を自動で検知したり、AIが氾濫を予測したりといった用途で既に実用化されています。これにより、これまで目視や断片的な情報収集に頼っていた災害対応に比べ、圧倒的なスピードと正確性で状況把握を可能にし、防災DXの実現に大きく貢献します。迅速かつ的確な情報提供は、命を守る行動や、効果的な救援活動へと直結します。
TRASCOPE-AIを活用した河川の水位検知・氾濫予測ソリューションについては、以下の記事で詳しく解説しています。

日常の設備監視から異常検知までをカバーする「MAIDOA plus」
災害は突如として発生するものですが、その前兆を捉えたり、日頃からの設備管理を徹底したりすることで、被害を最小限に抑えることができます。MAIDOA plusは、IoT技術を活用し、設備の異常検知・予兆保全を可能にします。
工場や施設の設備にセンサーを取り付けることで、温度、湿度、振動、漏水などの異常をリアルタイムで検知し、管理者へ通知します。たとえば、センサーによる漏水の早期発見は浸水被害の拡大を防ぎ、設備の異常な発熱検知は火災の未然防止に繋がります。
また、環境モニタリングや、設備の稼働状況を常時監視することで、故障による停止リスクを低減し、災害発生時の事業継続性を高めます。MAIDOA plusは、日常的な防災対策をデジタル化することで、より強靭な基盤の構築をサポートし、平時からの防災DXを推進します。
防災DXは、未来の防災対策において極めて重要です。その目的や効果を明確にすることで、導入検討をより効率的に進めることができます。
お役立ち資料
本記事に関する資料をダウンロードいただけます。