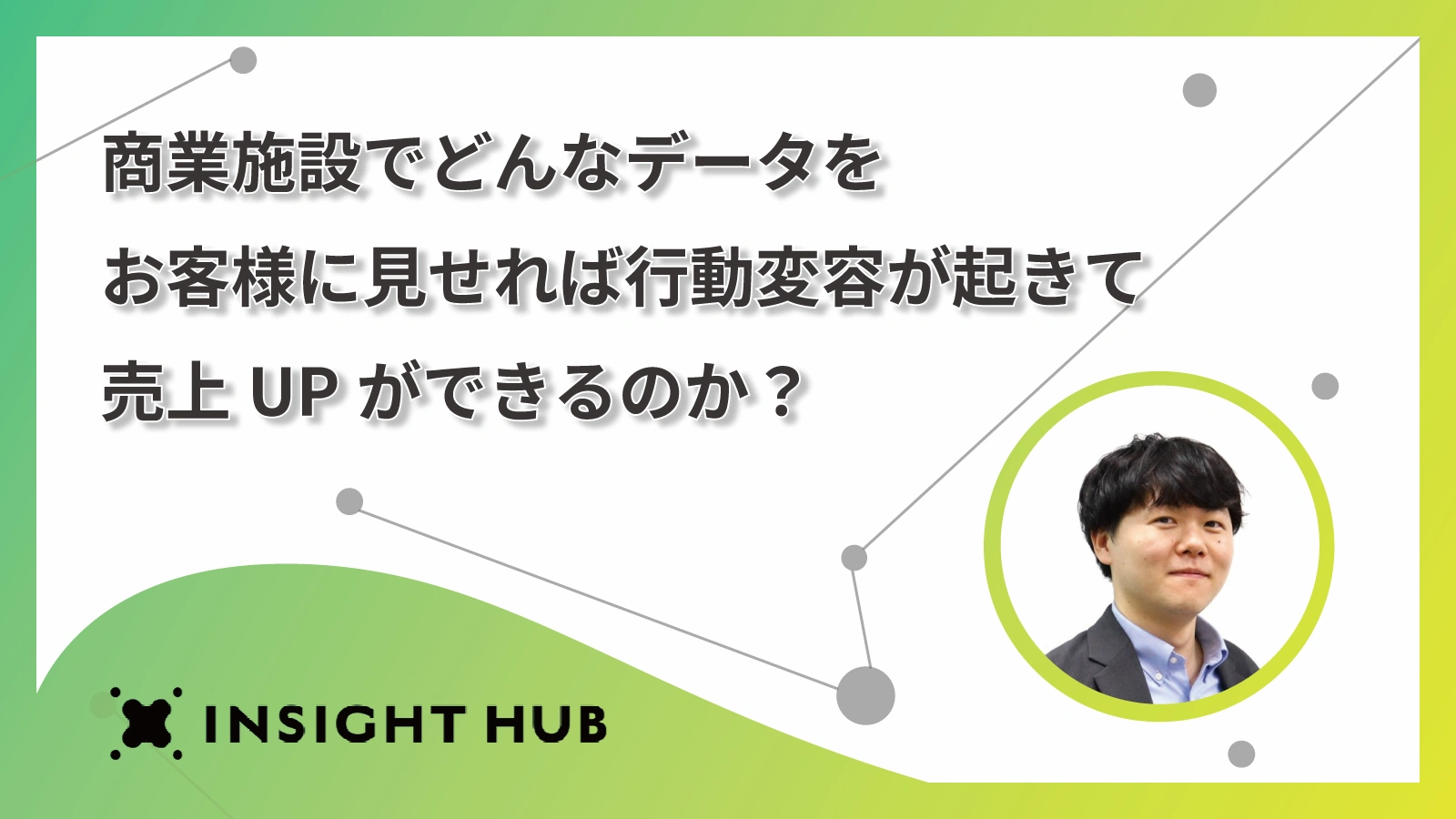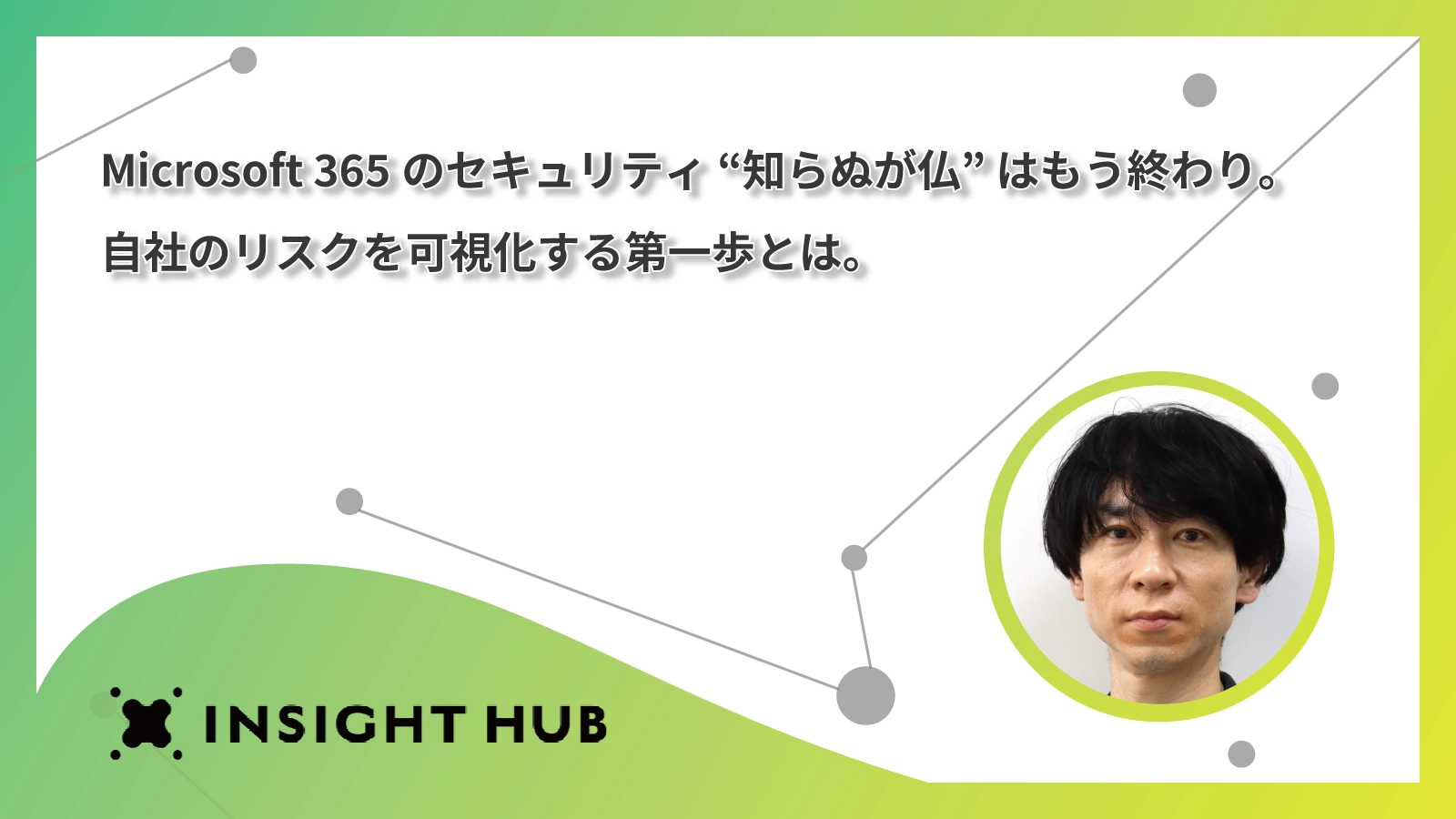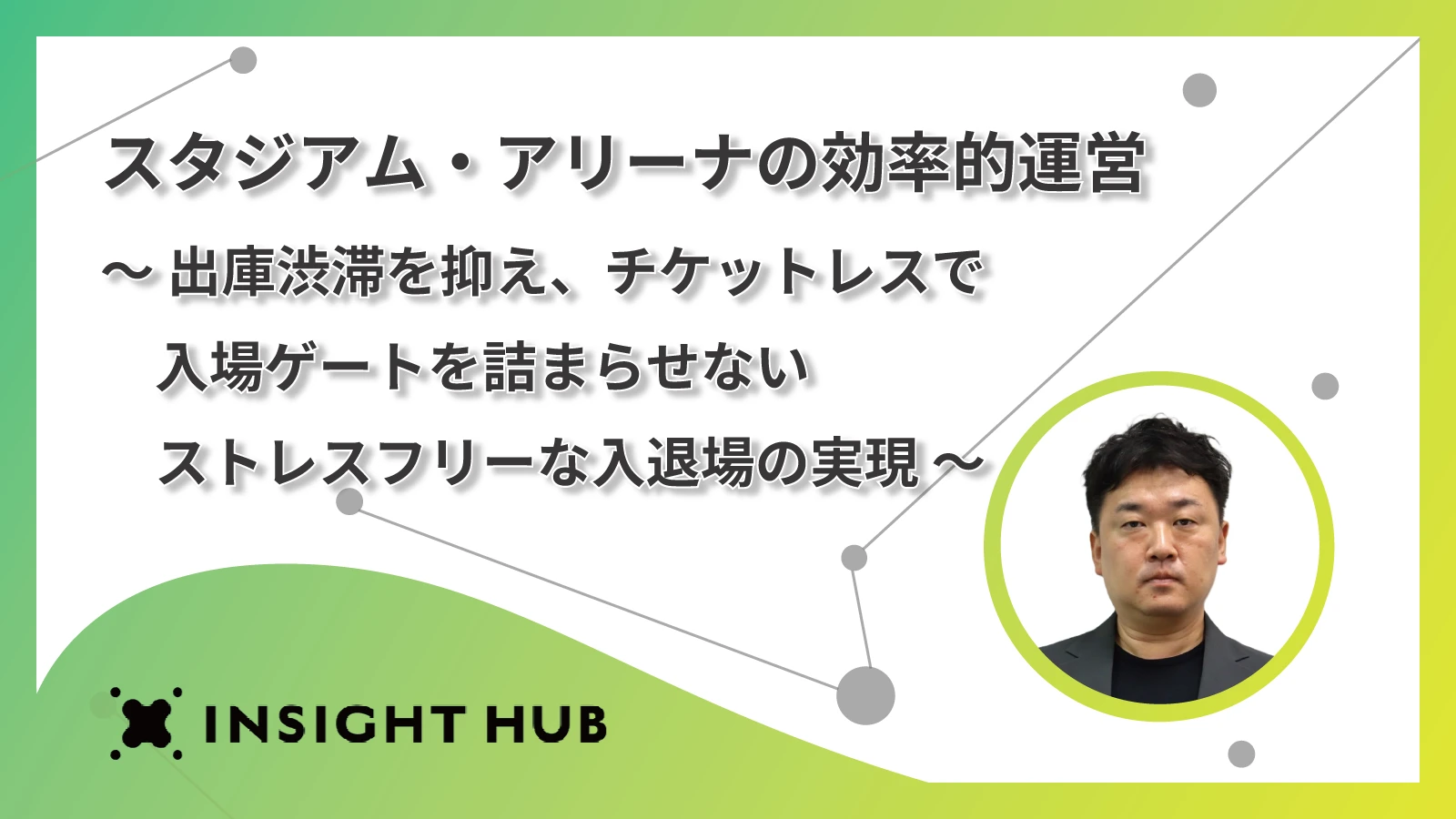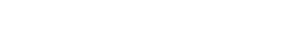近年、地球温暖化の影響による猛暑日の増加は、社会全体、特に労働現場における深刻な課題となっている。特に熱中症は、単なる体調不良にとどまらず、重篤な健康被害や生命の危機に直結する可能性があり、昨今法整備がされたこともあり、その対策は企業にとって喫緊の課題の一つである。
本稿では、丸紅I-DIGIOが提供する垂直統合型IoTサービス「MAIDOA plus」をプラットフォームとしたデータドリブンな熱中症対策の実現について、丸紅I-DIGIOグループ IT基盤サービスセグメント エッジソリューション事業室 大塚 直樹に話を聞いた。
熱中症対策の重要性とその背景
――昨今、企業における熱中症対策の実施が重要課題になっています。その背景・要因はどのようなものでしょうか。
大塚 職場における熱中症対策の重要性は年々高まっていますが、特に大きな要因として、2025年6月から施行された改正労働安全衛生規則に基づく、企業への対策の義務化です。また法規制がなかったとしても、企業として従業員の生命と健康を守るという人道的な観点はもちろん、企業の社会的責任(CSR)や生産性維持といった経営的な観点からも、重要視されてしかるべき課題だといえると思います。

熱中症は、高温多湿な環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調節機能がうまく働かなくなったりすることで生じるさまざまな症状の総称ですが、初期症状としてはめまいや立ちくらみ、筋肉痛などが挙げられます。こうした症状が進行すると頭痛、吐き気、倦怠感、さらには意識障害や痙攣といった重篤な状態に陥ることもあり、最悪の場合には死に至るリスクもあります。このような深刻な事態を未然に防ぐことは、今日においては企業が果たすべき最も基本的な責務の一つだといっても過言ではないと思います。
熱中症発症の要因については、大きく3つに分けて捉えることができます。
一つは環境要因です。気温や湿度、日差しの強さ、風通しの良し悪しといった、その人が置かれている環境です。特に建設現場や高所作業などといった屋外や、屋内でも工場や倉庫など籠りやすい場所において、高温下での作業環境は熱中症のリスクが高い環境といえます。
二つ目は身体要因です。個人の健康状態や体質、また持病の有無、睡眠不足、二日酔いなどのその日の体調、さらには暑さに対する耐性の個人差など、身体要因について個人差はありますが、大きなリスク要因となります。
そして三つ目が行動要因です。激しい運動や長時間の労働、水分補給の不足といった行動的側面のことで、体を酷使する作業や、休憩を取りづらい業務環境は、発症リスクを高めることにつながり得ます。
こうした要因が複雑に絡み合うため、同じ環境下で同じ作業をしていても、人によって発症のリスクは異なりますので、より個別的で精緻なアプローチが熱中症対策には求められます。
効果的な熱中症対策実現のための課題と、その解決策としてのAI・IoTの活用可能性
――そうした複雑な要因が絡み合う中で、効果的に熱中症対策を実現するための課題や、AI・IoTの活用可能性についてお教えください。
大塚 従来行われてきた熱中症対策の多くは、一律的なものが多く、すでに触れたように耐性の問題や、体調などの個人差がある中では、一律的な対策では十分とはいえませんでした。
また体調不良が生じたような場合でも、多くの職場では、従業員本人の自己申告に頼っている部分もあります。しかし熱中症は自覚症状がないまま進行することもあり、本人の感覚だけに依存する管理方法は、とてもリスクが高いといえます。
こうした課題を克服する上で、AIやIoTを活用したデータドリブンなアプローチが非常に有効であるといえます。
たとえば、バイタルウォッチなどのウェアラブルセンサーを活用することで、個人の体温や心拍数といった「バイタルデータ」を正確に収集できます。また、温度センサーや湿度センサーなどの環境センサーを使えば、職場内の温度や湿度といった「環境データ」もリアルタイムかつ客観的に取得することが可能です。これらの客観的なデータをもとに、自己申告に頼ることなく、個人の体調や環境の変化を的確に把握し、熱中症の発症を未然に防ぐことが期待できます。
もちろん、そのためには、収集した膨大なデータを一元的に管理し、分析・活用できるデータプラットフォームが不可欠です。たとえば、MAIDOA plusを利用すれば、こうしたデータの有効活用が可能となります。MAIDOA plus上では、管理者がダッシュボードなどを通じてリアルタイムの状況を直感的に把握できます。また、特定の指標データがあらかじめ設定した基準を超えた場合には、管理者にアラートを通知し、危険な状態を早期に把握して迅速な対応につなげることもできます。
このように、IoTで客観的データを収集し、MAIDOA plusのようなプラットフォームで統合管理し、場合によってはAIで高度な分析・予測を行うという一連の流れは、従来の対策が抱えていた課題を根本から解決し得る施策だといえます。まさに、データに基づく「データドリブンな熱中症対策」への転換といえます。
MAIDOA plusとバイタルウォッチの連携による熱中症対策について
――MAIDOA plusとバイタルウォッチの連携についてお教えください。
大塚 バイタルウォッチは、手首に装着するだけで体温、心拍数、血圧といった個人のバイタルデータを継続的に測定・記録できるウェアラブルデバイスです。これにより得られるさまざまなデータは、作業中の従業員の身体的な変化を客観的に捉え、熱中症の兆候を早期に検知するための貴重なデータとなります。
ただし、バイタルウォッチを全員に装着させるだけでは対策として限界があります。当該のデバイスが、異常を検知しても本人にのみアラートを発する仕様となっている場合、もし本人がそのアラートを無視したり、意識が朦朧として気づかなかったりした場合は、有効性を欠いてしまいます。
MAIDOA plusは、さまざまなセンサーや、そこから得られるデータを一元的に集約・管理できます。そこで、バイタルウォッチから得られるデータをMAIDOA plusで管理することにより、組織的に適切な管理が可能になります。
バイタルウォッチで収集されたデータは、MAIDOA plusのプラットフォームにリアルタイムで連携され、たとえば個人ごとに設定されたリスク閾値を超えたと判断した場合、本人への通知に加えて、予め設定された管理者や安全担当者にも即座にアラートが発報されます。これにより、管理者は現場に不在でも従業員の異常を迅速に察知し、休憩を指示したり、現場に駆けつけたりといった適切な介入を行うことができます。

また、MAIDOA plusは、収集・蓄積されたデータを多面的に集計・分析することで、部署ごと、現場ごとに、また個人ごとの個別性の高い管理をすることも可能です。「このエリアは特に高温になりやすく、所属する従業員の熱中症リスクが高い」といった分析結果に基づき、より負荷の少ない作業手順への見直しや、熱中症耐性の低い従業員の配置変更を実施して、リスク軽減を図るなど、データに基づいた人員配置や労働環境改善の検討にもつながり、職場全体の安全レベルを向上させることにもつながり得ます。
MAIDOA plusとBEMS(Building Energy Management System)の連携による熱中症対策について
――MAIDOA plusとBEMSを連携させることも可能だと伺いました。
大塚 BEMSは、ビル内のエネルギー使用量を最適化するためのシステムで、その主要な機能の一つに空調設備の制御などがあります。当社でも、MAIDOA plusを活用したBEMSのサービスを提供しています。センサーで室内の温度や湿度を監視し、設定された快適な状態を維持するように、冷暖房や換気を自動でコントロールし、建物全体のエネルギーコストの削減に寄与したり、そこで働く人々にとって快適な空間の提供を両立させたりしています。
従来のBEMSは、あくまで「空間」を対象として温度や湿度を一定に保つことを目的としていましたが、今後はMAIDOA plusとのさらなる連携により、「その空間にいる『人』がどのような状態にあるか」というデータを加味した管理が可能になります。
このようなBEMSとの連携によって、「体を動かしている従業員が多いエリアは、設定温度を通常より低くする」といった、人の活動状況に応じた動的な環境制御も可能になります。
このように、MAIDOA plusをハブとして、ミクロな「個人」のデータとマクロな「環境」のデータを連携させることは、熱中症リスクを多角的に分析し、より本質的で効果の高い対策を講じるための基盤を構築してくれます。
MAIDOA plusのさらなる活用可能性について
――MAIDOA plusの、さらなる活用可能性についてお教えください。
大塚 MAIDOA plusの真の価値は、特定のメーカーやデバイスに縛られない「オープンな共通プラットフォーム」であるというところにあります。つまり、熱中症対策という特定の用途に留まらない、圧倒的な拡張性と柔軟性を備えたソリューションであるということです。
IoTの世界は日進月歩であり、新しいセンサーやデバイスが次々と登場します。特定のベンダーの製品にしか対応しないシステムでは、こうした技術の進化に追随できず、すぐに陳腐化してしまうリスクがあります。この点、MAIDOA plusは、多様なメーカーのさまざまなセンサーやデバイスとも連携できるので、常に最適なツールを活用して、統合管理することができます。これは、当社が提唱する「10年後も使えるプラットフォーム」というコンセプトを具現化するものであり、MAIDOA plusの大きな活用メリットであると自負しています。熱中症対策を起点としたMAIDOA plusの導入であったとしても、それ以外の、企業の抱えるさまざまな課題解決に活用いただくことも可能となります。
また当社としては、MAIDOA plusの導入後も、お客様と継続的に対話し、新たなセンサーの登場や技術の進化を踏まえた新しい活用法を提案したり、あるいはお客様が抱える独自の課題に対して、「このデータをこのように分析すれば解決できるのではないか」といったコンサルティングを行い、共にソリューションを創り上げていくという、継続的な伴走支援と共創の姿勢を重視しています。この点も、「10年後も使えるプラットフォーム」の具現化に寄与する取り組みであると自負しています。
――熱中症対策という喫緊の課題に対して、MAIDOA plusは、バイタルウォッチやBEMSといった多様なデータソースを統合管理するプラットフォームとして、効果的・効率的なソリューションを提供することが可能である。しかし、その真価は熱中症対策に限定されるものではなく、労働安全、業務効率、健康経営といった、企業の持続的成長に不可欠な領域においても、十分に活用が可能である。MAIDOA plusの導入は、企業全体のさらなるデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させる手段としても有効といえそうだ。
お役立ち資料
本記事に関する資料をダウンロードいただけます。